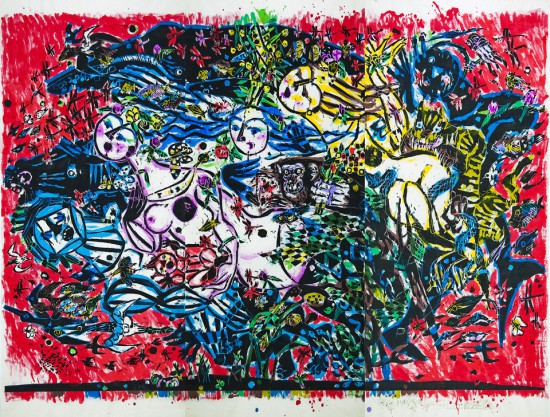ラン&スパ&○○○&トレイン
Posted in ブログ on 11月 10th, 2015 by ichiro – ラン&スパ&○○○&トレイン はコメントを受け付けていません2016年2月14日のサンシャインマラソンに向けて、
11月に入りようやく始動。
新川をいつものようにさかのぼるようにして走る。

夏井川では白鳥の飛来と鮭の遡上がはじまっていたが、
ここ新川は桜の紅葉がきれいだった。
走ってはでもすぐに歩く。
歩かざるをえない。
運動不足で。

ほとんど歩いて坂を越え湯本に着くと、
なぜだかリングが駅前に設置してある。
「教頭いけ~」
どうも青空プロレスで覆面レスラーにたたきのめされているのは、
声援からすると教頭のよう。
元気な教頭、いいですね~
ラリアートで一矢報いると、
坊主頭連中の声援がとぶ。(青春ですね)

「さはこ」と双璧の「みゆき」の湯はしばらく閉鎖されていたが、
無事ふっかつ。
そしてどうも今日はお祭りのよう。
「湯の街復興学園祭」とのぼりが出ている。
ハワイアンセンターで有名なこの街は駅前も熱い。
熱いといえば「みゆきの湯」は
左側の浴槽がとにかく熱い。
でも先月、
二本松の岳温泉で入った湯船は、
相当覚悟してもほんのちょびっとずつしか入れないほど熱かった。

でも「湯本」だって「岳」に負けてはいない。
どちらも全国4位の温泉数をほこる、福島県の底力である。
(ちなみに1位は長野、新潟、北海道とつづく。熱さランキングなどあれば面白い気もするが)

すっかりのぼせて飲む〇〇〇はやっぱりうまい。
慢性的な、首の痛みもすこしはやわらぐ気がする。
駅前では美女たちがステージで踊っていた。
さすがハワイアンセンターの街である。
すっかりハワイアンズのダンスチームと思ってみていたら、
舞台を降りるときのアナウンスを聞いて「高校生」と知った。
化粧をしているとどう見たって大人にしかみえない。
たまげた。(←すっかりおじさんの感想)
その次に上がったアイドルたちは、いわき出身で有名なのだそうだ。
どう見てもAKBにしか見えなかった。(←これもまたおっさんの感想)

およそ1年ぶりにこのラン&スパ&〇〇〇&トレインひとり上手ツアーを開催したので、
新しく生まれ変わった湯本駅にもはじめて入った。

すっかり洒落た佇まいで、
この駅のホームに直接面した足湯も画期的だが、
湯につかりながら振り返れば背後に窓があって、
いわき名産の「カジキメンチ」だって、スイーツだって、〇〇〇だって何でも頼めるシステム。
やりますね。湯本。
やってくれますね。JR。
さすがにおかわりはがまんしましたが。
そして帰りは9分のトレイン旅。
1時間以上かかってたどり着いた路もあっという間。
やはりこの王道(邪道?)トレーニングは、
今年もやめられそうにありません。